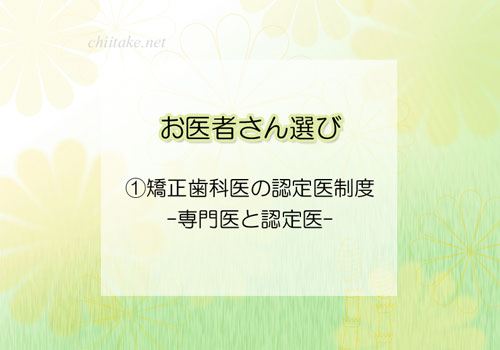私が矯正歯科を探し始めたのは2016年の春のこと。
徹底的に調べた後、6月から8月にかけて
無料カウンセリングを受けました。
※私は3件回りました。
悩みに悩み、
10月にお世話になる矯正歯科を決め、
今現在、矯正治療中です。
歯医者選びは本ッ当に慎重になりました。
【○○矯正歯科】という風に
歯列矯正オンリーだとひと目で分かる歯医者さんもあれば、
【○○一般歯科・矯正歯科】の看板を掲げる
歯医者さんも数多くあり
どうやって選べば良いのか悩みました。
数が多すぎて1箇所に決められるか不安でした。
そこで今日は自分がどうやって
今の矯正歯科を見つけたのか、
矯正歯科探しの際、参考にした
歯科矯正の認定医制度
を中心に書いてきます。
よろしければ参考にして下さい。
この記事に書いてあること
・歯列矯正に関する国家資格や免許は存在しない
・認定医制度について
・矯正歯科学会のこと
・歯科矯正の認定医と専門医の違い
・認定医や専門医はあくまでも目安にすること
歯列矯正に関する国家資格や免許は存在しないけど…
歯科矯正には資格制度があった
情報収集をしている時、ふと、
歯科医師免許とは別に
『矯正歯科医師免許』があるんじゃないかと
思いました。
ところが、その様な国家資格や免許は
ありませんでした。
つまり、歯科医師免許を所持していれば
誰でも矯正治療が出来る…というわけです。
(非常に驚きました。)
そうして調べていくうちに見つけたのが
これから紹介する『認定医制度』でした。
医学・歯学における認定医制度とは
医学・歯学において
学会認定専門医制度を導入している学会
というものが存在します。
学会認定専門医(がっかいにんていせんもんい、英語: medical specialist)とは、医学・歯学の高度化・専門化に伴い、その診療科や分野において高度な知識や技量、経験を持つ医師・歯科医師のこと。
登録医、認定医、専門医、指導医など細分化された区分が設けられているのが一般であり、各医歯学系学会が認定・付与し、現在約50の学会が本制度を設け、のべ2万4千人ほどの医師・歯科医師が認定を受けている。
出典:学会認定専門医 – Wikipedia
Wikipediaの内容をまとめると、
各学会に登録した医師・歯科医師は
自分の所属する学会の条件(一定年数の研修、実習や講義での単位取得、等)を満たし、
所属学会の出す試験に合格することで
認定医や専門医として認定される
この様な制度であり、
また、
『認定医/専門医の資格を取得する』と
記載しているサイトも多数あることから
一種の資格制度ともいえるでしょう。
つまり、
矯正治療の認定医に認定されている歯科医師は
矯正治療に関する知識や経験を持っている
ということが分かります。
矯正歯科学会
上記ウィキペディア内で
矯正歯科学会が3つ紹介されていたので
公式サイトのリンクを載せておきます。
※『矯正』の文字が入っている学会のみとします
各ページ内に
その学会に所属する矯正医と診療機関を
紹介しているページがあります。
ちなみに私は
『公益社団法人 日本矯正歯科学会』内から
矯正歯科を探しました。
認定医・専門医の違い
歯科矯正の認定医制度を詳しく調べると
認定医の他に『専門医』『指導医』の
ワードが出てきます。
認定医・専門医・指導医の違いはなんだろう?
自分なりに調べた結果、
1.指導医 > 2.専門医 > 3.認定医
の順になり、
指導医は専門医と認定医を指導し、
専門医は認定医を指導できる立場にあることから
左にいけばいくほど
歯列矯正の治療経験や知識・技術が高いことが
分かりました。
では、認定医や専門医は
どの様にして認定されるのか、
その辺を掘り下げてみます。
(指導医については割愛いたします。)
歯科矯正の認定医になるには
まず、認定医になる為には
所属する学会の条件を満たさなければなりません。
その『条件』とはどういうものか。
ここでは『公益社団法人 日本矯正歯科学会』の
認定医制度規則を参考に、
簡易的にまとめました。
歯科医師免許を取得後、
5年以上にわたり学会に所属し、
基礎研修 + 臨床研修( 又は 指導医・専門医の元で指導)を受け、
論文を発表し、
5年ごとに認定医の更新を行うこと
研修期間について具体的に記載しているページがあったので
引用させていただきます。
■「日本矯正歯科学会認定医」になるまで
出典:矯正歯科医師になるには研修期間が大事 – 勤務医のための歯科医師紹介サイト
ここまでの長い研修期間を経て、最終的に指導医もしくは専門医が認定試験の受験資格があるか判断します。そして初めて矯正歯科認定医の試験を受けることができるのです。最短でも歯学部6年、卒後研修医1年、矯正歯科基礎研修医2年、矯正歯科臨床研修3年と考えると、12年かかってようやく「認定医」になれるのです。
認定医になれば1人前の「矯正歯科医師」として活躍できます。
歯学部を卒業後に歯科医師免許を取得、
そこから卒後臨床研修を1年以上受けた後に
各大学の矯正学教室に入局、
そこで最低2年、大学によっては3年の
基礎研修を受ける、
[参考] 矯正歯科医師になるには研修期間が大事「■矯正歯科基礎研修期間」
基礎研修が終了したら、
さらに最低3年間の臨床研修を受ける、
もしくは指導医・専門医のいる歯科医院で
働きながら研修することも可能
[参考] 矯正歯科医師になるには研修期間が大事「■基礎研修後の臨床研修期間」
認定医になるためには最短でも12年かかり、
その後も5年ごとの更新手続きが必要になります。
その更新手続きにも『審査』があり
その審査に通らなければ認定医の更新がなされません。
一度認定医になったらそれで終わり…
ではないということです。
歯科矯正における専門医について
続いて、専門医についてです。
専門医も認定医同様、
『専門医制度』というものがあります。
近年、新たに『日本矯正歯科専門医機関』が設置され
専門医制度が統一されています。
[公式リンク] 日本矯正歯科専門医機関
専門医には専門医になる為の条件があり、
それを満たさなければ
専門医として認定されません。
その条件に関しては割愛いたしますが、
専門医の条件は認定医と比べ とても厳しく、
そのことから専門医は
認定医よりも豊富な治療経験と
高レベルな知識や技術をもっている
歯科医師ということになります。
「専門医」は、医師が実際に今まで治療をおこなった患者さんの症例を学会等の審査員が技術審査をおこない、合格した場合に得られる資格です。各団体とも厳しい基準を設けており、合格するには豊富な治療経験と高度な知識・技術が必要です。
これに対し「認定医」は、矯正の研修期間などの一定条件を満たした医師が書類審査等で認定される比較的簡易的な資格であり、矯正医として最低限必要なレベルといえるでしょう。
出典:「専門医」と「認定医」の違い – e-矯正歯科.com
また、専門医も5年ごとに更新があり
その際も厳しい審査をクリアしなければなりません。
全国に約10万人いる歯科医師のうち、
矯正の学会や団体に所属している矯正医は約8千人、
矯正医専門医は矯正医の約6%と少ない割合ですが、
それだけ審査を通るのが難しい資格といえます。
[参考] 「矯正専門医」の資格とは – 口コミ歯科・歯医者
[2022年現在]
認定医制度はあくまでも参考に…
認定医・専門医の資格は各学会に所属することで
得られる資格でありますが、
矯正治療を行っていても
学会に所属していないお医者様も存在します。
逆に、
専門医・認定医の資格を持っていても
それはあくまでも
『矯正治療に特化している』という
判断材料にはなるけれど
必ずしも矯正治療が成功する or
自分の納得いく結果に繋がるかどうかは
分かりません。
認定医制度以外にも
口コミを見たり、
医院のホームページを見て
先生や院内の雰囲気を掴んだり、
矯正治療をしたことのある知人友人から話を聞いたり、
カウンセリングを受ける、など、
様々な視点から判断することも
必要だと私は思います。
特に、
矯正治療は長い年月をかけて行うものなので
資格の有無に囚われるだけでなく
先生との相性(コミュニケーションが取りやすい)の方が
重要になってきます。
これから矯正を始める方々が
「この先生にお願いしたいな。」と
思える先生に出会えることを
切に願っています(^^)
ちなみに、
私は3件の矯正歯科でカウンセリングを受け、
そのうちの1件に決めました。
どうやって今の矯正歯科を探したのか、
どうやってカウンセリングを受ける歯医者を
見つけたのかはこちらの記事に書いています。
あわせて読みたい 出っ歯の矯正歯科探し 『自分なりの条件を決める』
よろしければ併せて参考にしてください(^^)
この記事を読んだ方はこちらの記事も見ています
~失敗しない矯正歯科選び~
カウンセリングを必ず受けた方が良い理由